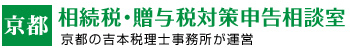【相続税の配偶者控除は1億6,000万円】適用要件、計算式、よくある質問を税理士解説

相続税の配偶者控除とは、死亡した人の配偶者が遺産を相続するときは、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからない制度のことです。
簡単に言い換えると、最低でも1億6,000万円までの相続なら配偶者は相続税がかかりません。
本記事では、相続税の配偶者控除の適用要件や計算式を中心に解説します。
配偶者控除に関するよくある質問にもQ&A形式でお答えしているので、ぜひお役立てください。
 | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除とは、死亡した人の配偶者が遺産を相続するときは、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからない制度のことです。
正確には、配偶者の税額の軽減として国税庁のホームページに記載されています。
法定相続分とは、民法で定められた相続の割合のことで、遺産分割協議をするときの目安になるものです。
以下のように相続の割合が相続人によって異なります。
▼法定相続分
| 配偶者のみが相続人のケース | 配偶者1 |
| 配偶者と子どもが相続人のケース | 配偶者2分の1 子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1 |
| 配偶者と父母または祖父母が相続人のケース | 配偶者3分の2 父母または祖父母(全員で)3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース | 配偶者4分の3 |
なお、法定相続人の範囲も民法により以下のように定められています。
▼法定相続人の範囲
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
| 第1順位 | 被相続人の子ども |
| 第2順位 | 被相続人の父母 (父母が死亡している場合は祖父母) |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 (兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪) |
たとえば、死亡した人に子どもがいるときは配偶者と子どもが相続人になるため、法定相続分は「配偶者と子どもが相続人のケース」の割合を参照します。
配偶者は常に相続人ですが、配偶者以外の人は順位が高い人が相続人になります。
死亡した人に子どもがいないときは父母、父母もいないときは祖父母、祖父母もいないときは兄弟姉妹と、家族構成によって相続人の範囲が変わる仕組みです。
配偶者控除を適用しなくても相続税がかからないケース
遺産総額が基礎控除額以下の場合は、配偶者控除を適用しなくても相続税はかかりません。
基礎控除額とは、遺産総額から差し引ける控除額のことで、計算方法は以下の通りです。
| 3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額 |
詳しくは、以下の記事で解説しています。
相続税の配偶者控除の適用要件
相続税の配偶者控除を適用するときは、以下の要件を満たす必要があります。
・法律上の配偶者であること ・相続税の申告期限までに遺産分割をすること ・税務署に相続税の申告書を提出すること |
順に解説します。
1.法律上の配偶者であること
配偶者控除は、法律上の配偶者が対象の制度です。
よって、内縁関係は法律上の配偶者ではないため、配偶者控除は適用できません。
法律上の配偶者であれば婚姻期間は問われません。
2.相続税の申告期限までに遺産分割をすること
配偶者控除は、配偶者が相続する遺産に対して適用するため、相続税の申告期限までに遺産分割をする必要があります。
相続税の申告期限は、死亡した日の翌日から10か月以内です。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添え、申告期限から3年以内に遺産分割を終えた場合は配偶者控除を適用できます。
申告期限の後に配偶者控除を適用するときは、遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」という手続きが必要です。
3.税務署に相続税の申告書を提出すること
配偶者控除を適用する手続きとして、税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。
配偶者控除を適用して相続税がかからないときも申告書の提出が必要です。
申告書には以下のような書類を添えて手続きをしましょう。
・戸籍謄本または法定相続情報一覧図 ・遺言書または遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの) ・申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限までに遺産分割ができない場合) |
相続税の配偶者控除の計算式(配偶者+子ども2人)
ここからは、配偶者控除を適用する場合の相続税の計算式を解説します。
以下の前提でシミュレーションします。
▼前提
| 遺産総額 | 2億円 |
| 相続人 | 配偶者+子ども2人の計3人 |
1.基礎控除額を計算する
最初に相続税がかかるかどうかの基準となる基礎控除額を計算します。
冒頭でも触れたように、基礎控除額は遺産総額から差し引くことができ、法定相続人の数によって差し引ける金額が変わります。
| 3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額 |
相続人が配偶者と子ども2人のとき、基礎控除額は4,800万円となります。
| 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
2.課税遺産総額を計算する
次に、遺産総額から1の基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。
| 遺産総額-基礎控除額=課税遺産総額 |
遺産総額が2億円で、基礎控除額が4,800万円のとき、課税遺産総額は1億5,200万円となり、1億5,200万円に相続税がかかります。
| 2億円-4,800万円=1億5,200万円 |
3.相続税の総額を計算する
次に、法定相続分で遺産分割したとして、(1)各相続人の仮の相続税額を計算します。
各相続人の仮の相続税額を合計したものが(2)相続税の総額です。
配偶者と子ども2人の仮の相続税額は、以下の金額になります。
| 計算式(1) | 課税遺産総額×法定相続分×税率-控除額=各相続人の仮の相続税額 |
| 配偶者 | 1億5,200万円×2分の1×30%-700万円=1,580万円 |
| 子ども1人あたり | 1億5,200万円×4分の1×20%-200万円=560万円 |
各相続人の仮の相続税額を合計すると、相続税の総額は2,700万円となります。
| 計算式(2) | 相続人の仮の相続税額+相続人の仮の相続税額+相続人の仮の相続税額=相続税の総額 |
| 相続税の総額 | 1,580万円+560万円+560万円=2,700万円 |
▼法定相続分
| 配偶者のみが相続人のケース | 配偶者1 |
| 配偶者と子どもが相続人のケース | 配偶者2分の1 子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1 |
| 配偶者と父母または祖父母が相続人のケース | 配偶者3分の2 父母または祖父母(全員で)3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース | 配偶者4分の3 |
▼相続税の税率・控除額
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4.各相続人の納税額を計算する
次に、3の相続税の総額に実際の相続の割合を当てはめて各相続人の納税額を計算します。
実際にも法定相続分の割合で相続したとすると、各相続人の納税額は以下の金額になります。
| 計算式 | 相続税の総額×〇%(実際の相続の割合)=各相続人の納税額 |
| 配偶者 | 2,700万円×50%(2分の1)=1,350万円 |
| 子ども1人あたり | 2,700万円×25%(4分の1)=675万円 |
配偶者控除を適用するときは、配偶者の納税額である1,350万円から配偶者控除の金額を差し引きます。
以下で計算した結果として、1億6,000万円または法定相続分の多い金額のどちらかまでは相続税がかからない仕組みです。
相続税の総額×((1)または(2)の少ない金額÷課税価格の合計額)=配偶者控除の金額 (1)課税価格の合計額×配偶者の法定相続分 (2)配偶者の課税価格 |
配偶者控除の金額は1,350万円となり、配偶者の納税額は0円となります。
2,700万円×(1億円÷2億円)=1,350万円 1,350万円-1,350万円=0円 |
相続税の配偶者控除のデメリット
相続税の配偶者控除のデメリットとして、配偶者が死亡したときに発生する次の相続(二次相続)で子どもの税負担が増える可能性が懸念されます。
配偶者控除を適用することで「配偶者控除の上限まで配偶者が遺産を相続すれば相続税が0円になるのでは?」と思われるかもしれませんが、子どもがいる場合は二次相続を踏まえて遺産分割をする必要があります。
二次相続で子どもの税負担が増える理由は、主に以下の通りです。
・配偶者控除が適用できない ・法定相続人が減り基礎控除額が少なくなる ・配偶者の個人の財産が加算される ・相続財産が増えれば税率が高くなる |
二次相続では配偶者控除が適用できないほか、配偶者が死亡すれば法定相続人が減り基礎控除額が少なくなります。
配偶者の個人の財産も加算されるため、今回の相続(一次相続)で配偶者が多額の遺産を相続すると子どもの負担する税率が高くなる場合があります。
よって、一次相続から二次相続を踏まえてトータルで相続税を減らせる選択を考えるべきです。
相続税の配偶者控除に関する【Q&A特集】
ここからは、相続税の配偶者控除に関するよくある質問にお答えします。
・配偶者がすべて相続した場合の相続税はいくら? ・相続税の配偶者控除は申告が不要? ・相続税の配偶者特別控除とは? ・配偶者控除を適用するときの申告書の書き方は? ・相続税の基礎控除と配偶者控除は併用できる? ・配偶者控除は申告期限を過ぎても適用できる? ・配偶者控除の適用前に配偶者が死亡したらどうなる? |
配偶者がすべて相続した場合の相続税はいくら?
配偶者がすべて相続した場合でも、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額までなら相続税は0円です。
なお、法定相続人が配偶者のみのときは、いくら相続しても相続税はかかりません。
配偶者のみが相続人のケースでは、法定相続分の割合が1となるためです。
相続税の配偶者控除は申告が不要?
配偶者控除は、相続税が0円でも申告が必要です。
申告が不要なときは、そもそも相続税がかからないときです。
相続税の配偶者特別控除とは?
相続税に「配偶者特別控除」はありません。
配偶者特別控除は、所得税の制度です。
配偶者控除を適用するときの申告書の書き方は?
配偶者控除を適用するときの申告書の書き方は、国税庁の資料を参考にするとよいでしょう。
相続税の申告は税理士に依頼することもできます。
国税庁:「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例
相続税の基礎控除と配偶者控除は併用できる?
相続税の基礎控除と配偶者控除は併用できます。
基礎控除は遺産総額から差し引き、配偶者控除は配偶者の納税額から差し引きます。
配偶者控除は申告期限を過ぎても適用できる?
相続税の申告期限が過ぎても、申告期限から3年以内に遺産分割を終えた場合は配偶者控除を適用できます。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添え、遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」という手続きが必要です。
配偶者控除の適用前に配偶者が死亡したらどうなる?
遺産分割協議の途中で配偶者が死亡した場合、一次相続での遺産分割は配偶者がいるものとして進めます(数次相続)。
死亡した配偶者の相続分は、配偶者控除を適用できます。
配偶者控除以外の相続税の税額控除一覧
配偶者控除以外の税額控除は、主に以下のようなものがあります。
相続税を減らすためには、税理士に相談しながら漏れなく適用しましょう。
| 未成年者控除 | 相続人が未成年のときに、相続税額から一定の金額を差し引ける制度 |
| 障害者控除 | 相続人が85歳未満の障害者のときに、相続税額から一定の金額を差し引ける制度 |
| 相次相続控除 | 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続税を納めていたときに、相続税額から一定の金額を差し引ける制度 |
| 贈与税額控除 | 相続税額からすでに納めている贈与税額を差し引ける制度 |
| 外国税額控除 | 国外の財産を相続し、国外で相続税に相当する税金が課されているときに一定の金額を控除できる制度 |
相続税のご相談は税理士法人吉本事務所へ

・相続税がかかるかわからない
・相続税がいくらかかるか知りたい
・相続税を減らすにはどうしたらよいか
・どのような特例や控除が使えるか
などのお悩みは、税理士法人吉本事務所へご相談ください!
当事務所には相続専門の税理士が在籍しており、相続税の計算、申告、相続材対策など全般のご相談・ご依頼を一貫してお受けしています。
特に長年の経験と知識を活かした相続税対策を強みとし、お客様にとってベストな選択をご提案いたしますのでどうぞご安心ください。
また、同じオフィスに行政書士が在籍しており、司法書士や弁護士とも常に連携しているため、相続の手続きやお悩みにも幅広く対応可能です。
相続税のご相談は初回無料でお受けしていますので、些細なことでもお気軽に税理士法人吉本事務所までご相談ください。
無料お見積り・お問い合わせフォームはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら:0120-101-628
(つながらない場合はこちら075-872-6255)
まとめ
相続税の配偶者控除を適用すると、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
とはいえ、子どもがいる場合は二次相続で子どもの税負担が増えないように注意して遺産分割をする必要があります。
遺産の分け方で税額が変わるため、後悔しないためにも税理士へ相談することをおすすめします。